SNSでちょっとした流行になった「7日間ブックカバーチャレンジ」。
趣旨は読書文化の普及に貢献するためで、好きな本の表紙を1日1冊、7日間投稿するというもの。
外出を控えたいこの頃、なかなかの好企画で、人様の投稿も楽しみながら拝見した。
自分が挙げた未読の書籍をまとめつつ、あわせて名著『読んでいない本について堂々と語る方法』をご紹介。
● 第1日目~第7日目 のブックカバーチャレンジ
● 『読んでない本について堂々と語る方法』 ピエール・バイヤール 著 を読む
● 第1日目~第7日目 のブックカバーチャレンジ
「7日間ブックカバーチャレンジ」のルール、~好きな本かつ表紙画像だけアップ~ということを生かして、積ん読本シリーズでピックアップしてみた。つまり未だ読んでいないものを選んでみた次第。これならお手軽で、7日間毎日選び続けることができそうだったからだ。
それに名著『読んでいない本について堂々と語る方法』にはこうある。
「書物において大事なものは書物の外側にある。なぜならその大事なものとは書物について語る瞬間であって、書物はそのための口実ないし方便だからである。」
つまり大事なのは本の表紙であると(笑)。他人の書いたブックカバーチャレンジを読んでいると、本は読むものではなくて、その人とその本の関わった背景や理由を楽しんでいることに他ならない。また、その人と作家の解釈という名の対話を読み取って楽しんでもいる訳でもある。だから、本は読まなくても充分楽しめる。そう言う意味でこの「7日間ブックカバーチャレンジ」の「本についての説明はナシで表紙画像だけアップ」というルールは秀逸だと感じた。
● 第1日目 『ディートリッヒ自伝』 マレーネ ディートリッヒ 著
女優さんの自伝というのはたいへん面白く大好物である。他にもミア・ファローやバーグマンなんかの自伝も控えているが、このところドイツ史への関心が高く、これもそろそろ読みたいなぁと書棚で目にとまった。
目次を見るとチャップリン、ヒッチコックにストラヴィンスキーまで出てくる。ディートリッヒがお付き合いしていたジャン・ギャバンには割かれているページ数も多そうだ。ヴァネッサ・レッドグレーヴの自伝でもフランコ・ネロについて赤裸々かつ懐かしみいっぱいで書いていたし、浅丘 ルリ子も「私は女優 」で元夫の石坂浩二への親しみを慈愛深くしたためているので、こういうお話はちょっと期待できる。それにディートリッヒは映画のイメージとは裏腹に、たいそうな料理上手だったらしく、その辺も知りたい。
浅草の古書店でこの本に出会った際、自伝なんて書く人なんだと意外に感じたことを覚えている。

● 第2日目 『バルチック艦隊の潰滅』 ノビコフ・プリボイ 著
2009年~2011年に放映されたNHK『坂の上の雲』をこの春に初めて観た。テレビの録画機能に10年間眠っていたことになる。やたら長い長編大作なのと、第13回の最終話だけをなぜか録画し損ねていた為、観る気になれずに放置していたのだった。
されど、ここ数年は帆船やら海戦やら船舶関係に興味があり、海事博物館巡りがライフワークに加わったので一気観してみた。そして、録画しはぐった最終話はNHKオンデマンドで補った。
柄本明の乃木希典があまりによい感じで旅順攻略あたりも目が離せない。そして、録画しそこねた最終話は圧巻の日本海海戦だが、ここでロシアのバルチック艦隊はこてんぱんにやられてしまう。それ故に逆側の立場の視点では如何に、と思い、高円寺の古書店の均一本棚にて購入。第一回スターリン賞の冠がほのかに眩しい(苦笑)。
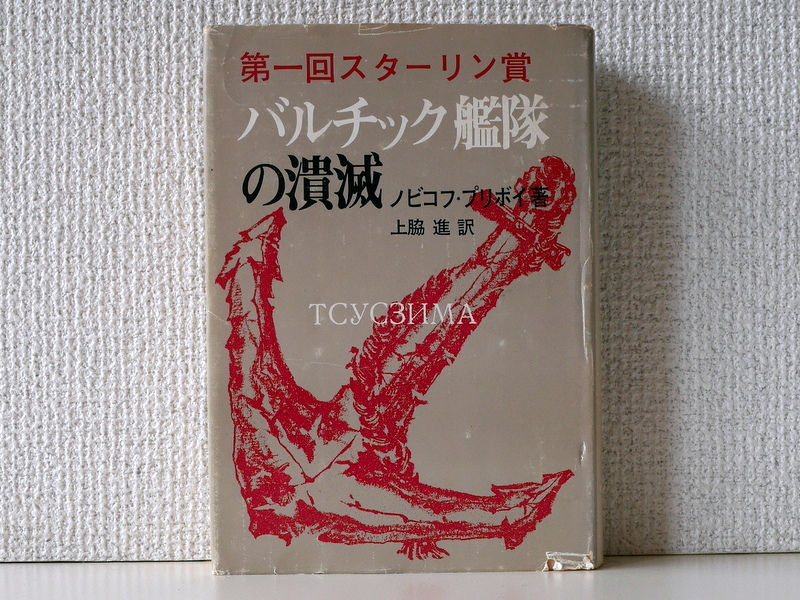
● 第3日目 『美の味わい』 エリック ロメール 著
表紙写真は映画『ストロンボリ』のバーグマン。帯には「ヌーヴェルヴァーグの正統を疾走しつつける男の映画論」とあり、ロッセリーニ、ヒッチコック、ベルイマン、ルノワールなどの評論がぎっしり。折しも映画専門チャンネル「ザ・シネマ」が『【生誕100年】レトロスペクティブ:エリック・ロメールの特集』を今月から組んでいる。そろそろ読もうかなと思った1冊。
ロメールと言えば、おじいちゃんが嬉々と子供や若者の恋愛映画を撮っているイメージだった。吉祥寺の古書店でこちらの本に出会い、こんな評論集を出していることに驚いた。内容は極めて真面目、自分の不案内を恥じる。

● 第4日目 『回想の第三帝国 ―反ヒトラー派将校の証言1932‐1945』 アレクサンダー・シュタールベルク 著
ドイツ国防軍「最高の頭脳」と言われたマンシュタイン元帥の副官の回想録。当時の国家の中枢に立ち会うことができた若者から見たナチスドイツ時代。彼はマンシュタインと常に行動し、スターリングラードにも同行している。貴重な時代の生き証人で反ヒトラー派でもあったらしい。
本の建付けは、同じ平凡社の(20世紀メモリアル)シリーズ『ダウニング街日記―首相チャーチルのかたわらで』にて、チャーチルの若き首相秘書官ジョン・コルヴィルが大戦中の国家の中枢の状況をしたためたものに似ているのかもしれない。チャーチルの奇人ぶりの描写とあいまって面白かったから、こちらの本も読む前から楽しみ。
古書価格では下巻がかなり高値推移しているが、たまたま上下巻揃いで格安本を神保町で発見し、嬉しくて即買いした。

● 第5日目 『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』 フランソワ・トリュフォー、アルフレッド・ヒッチコック 著
ミルクの白さ。映画内でケーリー・グラントが真っ白なミルクをお盆に載せ階段をあがってくる。このお盆に載ったミルクへ観客の視線が集るように、ミルクの白を際立たせる。「スポットライトをあてたのか」と尋ねるトリフォー、「いや、コップの中に豆電球を仕込んだんだ」と答えるヒッチコック。この話を何かで知って、学生時代からずっと読みたいと思っていた本。
映画『ヒッチコック/トリュフォー』を観て、まあ、この本は大きく値段が下がらないし潮時かなと思って、どこかの古書店で比較的安価なものを購入した。しかし、ぶ厚すぎて、今だに未読状態。でも、数十年間も気になっていた本だけに、自宅の書棚に鎮座しているだけで安心感をもたらしてくれる。
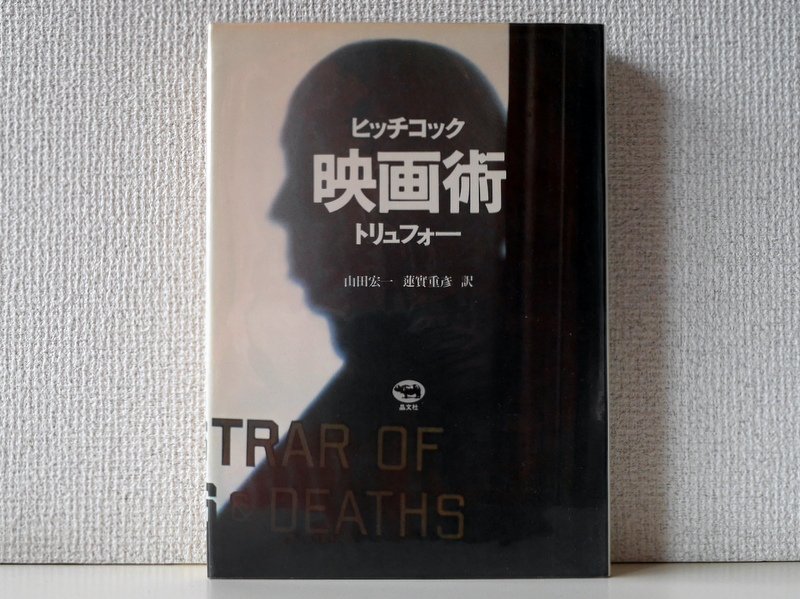
● 第6日目 『奇妙な戦争―戦中日記Novembre 1939‐Mars 1940』 ジャン=ポール・サルトル 著
戦中の日記で1939年11月から1940年5月までの間の日記、つまりドイツのポーランド侵攻が39年9月でフランス侵攻が40年5月だから、その間の北欧やオランダ、ベルギーなど戦火が拡がっていく最中の日記になる。ちょうど同じ頃を描いたイレーヌ・ネミロフスキーの小説『フランス組曲』やジャン・コクトーの『占領下日記1942‐1945』を読んで、手を伸ばしたと記憶している。
戦中日記は他にも数多あり、ジャーナリスト清沢 洌の『暗黒日記』やドイツ人作家『ケストナーの終戦日記』、好きな作家 久生十蘭の『従軍日記』なんかも書棚に控えている。戦争のような大きな出来事について歴史書は俯瞰し、高所から描いてしまうので、日記による日々の生活を踏まえた個々人の目から見た世界は新鮮。戦時下においては、身分や場所によって境遇が様変わりするので、こういった個々の視点を知るのは貴重とも言える。
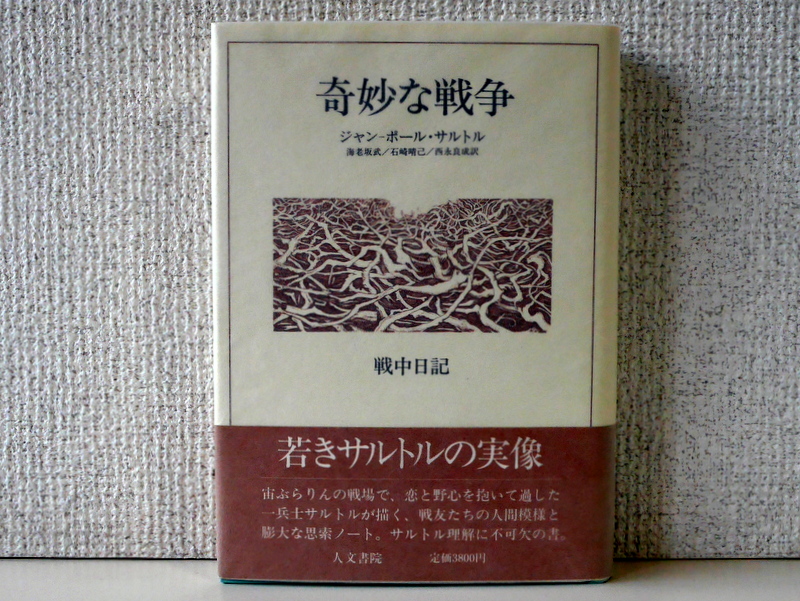
● 第7日目 『タルコフスキー日記―殉教録』 アンドレイ・タルコフスキー 著
1970年から1986年までの日記、古書店でパラパラとページをめくって「ソラリス」や「ノスタルジア」などの言葉が目に入ってくる。更には、監督の幼い頃の田舎村の写真や自筆の画なども挿入されており、本文には気になる一節もあった。背表紙の値段を見ると、高い・・・(笑)。
この立ち読みの際に、ひっかかった本文の一節がどうしても思い出せない。下北沢の広い古書店で、置いてあった書棚の位置まで覚えているのに。とにかくこの一節が響いてしまい購入した。いずれタルコフスキーの作品を観直す際に読もうと思う。
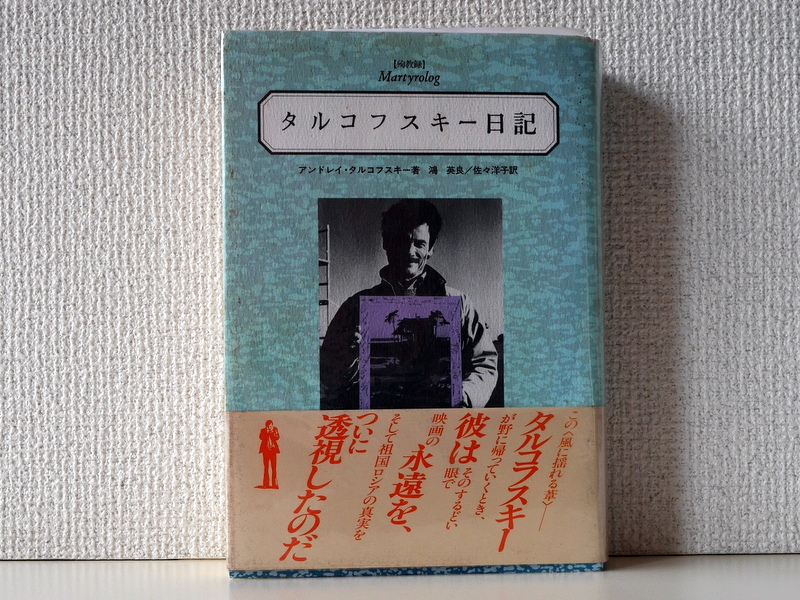
● 『読んでない本について堂々と語る方法』 ピエール・バイヤール 著を読む
そして、冒頭に引用した『読んでない本について堂々と語る方法』、なんとも不道徳なタイトル。しかし、読み終える頃には、圧巻の理屈と説得力をもって、自らも読んでない本を語ろうとし、大団円を迎える知的サスペンス。壮大な読書のメカニズムを説き明かす羞恥心なき果敢な試みに拍手喝采であった。
とにもかくにも、本書は読書行為なるものを掘り下げまくり、面白くて一気に読破した。著者はパリ大の先生、しかも文学部。なのにこのタイトル(笑)。
『読書は神聖にして、神聖とされる本を読まねば人に軽んじられる / 飛ばし読みや流し読みは軽蔑の対象、プルーストを流し読みしたという文学者はいない / 本を読まなければ、その本について語る資格がない』以上が読書の3常識。この常識を恥ずかしげもなく覆し、著者は、読書という行為について語りまくる。

自分も大いに経験があることだが、観たそばから内容もキャスティングも忘れてしまう映画たち、画集を見ても思い出せない、かつて美術館で観賞したはずの名画ら、そして読後早々に語られているコンテンツが忘却の彼方にすっ飛ぶ書籍群。誰もが気になる事柄である。しかし、このような忘却癖を、モンテーニュを題材にして、著者は我々を勇気つけてくれる。「仕方ないことだ」と。
書籍の内容を説明するには、読んでいることが、かえって弊害を招く???なんて話から始まり、『教養があるかどうかは、なによりもまず自分を方向づけることができるかどうかにかかっている。教養があるとは、しかじかの本を読んだことがあるということではない。そうではなくて、全体のなかで自分がどの位置にいるかがわかっていること。』などと、インターネットの大海に生きる私たちには、金科玉条になりうる名言で導いてくれる。そう、自分の方向や立ち位置を知ることが読書の役割なのかも、と。

『本についての会話は、その本についてだけでなく、もっと広い範囲のひとまとまりの本について交わされる。それは、ある時点で、ある文化の方向性を決定づけている一連の重要書の全体である。』これを「共有図書館」と名付け、これこそが大切であると説く著者。個別の書物を読んだか、読んでいないか、内容を覚えているか、覚えていないか、なぞ問題ではない、とズンズン論は進む。
おもしろかったのは、アフリカの部族に「ハムレット」を理解してもらう話。欧州人より彼らのほうが遙かに合理的な考え方をしており、話がかみ合わない。亡霊の話では、部族の酋長に「死人が歩けるわけないだろう」と反論され説明に窮する(笑)。要は、部族の独自の価値観があるので、同じテクストでも同じように解釈されるとはかぎらない、むしろ改変されていくのだ、と。それが解釈の豊かさの契機である、と。そして、その章のタイトルは「教師の面前で」(笑)。
刺激的な挿話が盛りたくさんで、その先は
・作家を前にして、読んでない本をコメントする場合、
・愛する人の前で、本に関する失言や知ったかぶりをするケース(この題材は名作映画、ビル・マーレーの『恋はデジャ・ブ(Groundhog Day)』)
と続き、有名な映画『薔薇の名前』や『第三の男』なども題材にした章が続く、そして、それらを題材にした、そんなこんなの講釈が楽しい。

ステマ、炎上商法で、本など読まねど、その書籍の価値の上げる手法については、バルザックを題材として説明がなされる。もう百花繚乱の眩い事例が続いて、飽きないのだ。
そして、大団円は「本を読んだ」という行為の不確かさこそが、創作活動に連なるという圧巻の結び。爽やかである。そして、教育に従事する者こそがそれを実践すべきと続く大胆さ。
なるほどなのだ。読書において大事なのは、本との関係性である、実は映画や絵画もそう。美術館に行くと、なにかを得よう学ぼうと鑑賞モードになる。そうではなく、本当は、絵も映画も対象との関係で、作家に問いかけたり、自分の変化を楽しむほうが遙かに健全だ。
美術館の企画展で数珠つなぎになって、絵画を斜め見しながら、ゾロゾロ作品の前を通り過ぎるのでは、対話は成り立たない。書籍も同じで、どことなく権威によって文字化された文章は神聖さを漂わせるが、目で字面を追って理解を装っているだけでは、駄目なのだ。

そして、書物との関係性を見いだすこと、対話を楽しむことができれば、その本ですら、読まなくたってよいのかもしれない。それを気づかせてくれる痛快な本であった。
尚、この本、翻訳がすばらしい。そして、これだけこなれた訳を付す訳者なので、あとがきも最期の結び含めて素敵すぎた。



