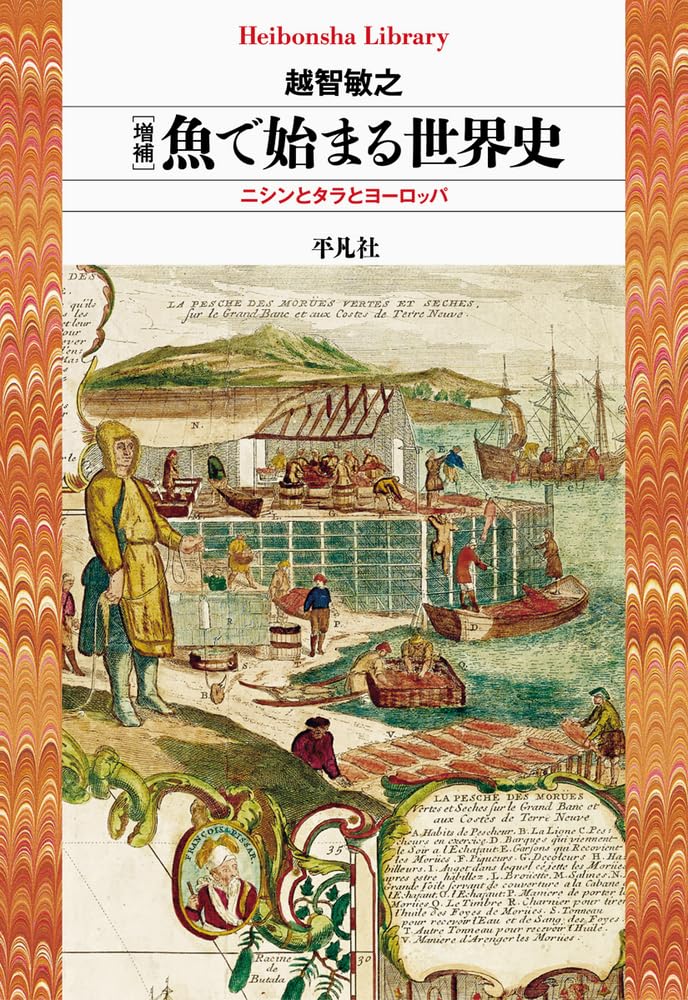欧州旅での食事はどうしてもお肉中心になってしまうが、旅先ではアパートを借りることが多いので、なるべく魚を調理したりして魚食に励むようにしている。港町ハンブルクでは魚サンドをパクついて、同じく港町のグダニスクでは市場の魚屋さんと仲良くなって、毎日お店に通いアパートでムニエルなんかをつくっていた。
こうして欧州で魚食をしているとオヒョウが高級魚なんてことを知ったり、北海やバルト海のお魚はとても美味しいことに気がつかされたりもする。
そして、このことをきっかけに欧州の魚に関する歴史を調べ始めることにした。初回のお話はウナギ/鰻である。日本のみならずウナギは栄養価も高く大量に捕れて安価であったので、かつて欧州でもよく食べられていた。
● 驚愕の面白さ『魚で始まる世界史: ニシンとタラとヨーロッパ』
● ロンドンのうなぎ屋は日本と大違い
● 怪しげな体液理論とフィッシュ・デイ
● 魚を食べないと国力が弱まる?
● 驚愕の面白さ『魚で始まる世界史: ニシンとタラとヨーロッパ』
欧州の魚食に関わる歴史を知る上で、とても参考になった書籍は『魚で始まる世界史: ニシンとタラとヨーロッパ』という本、かなりの名著である。著者はシェイクスピア研究の学者さんらしく歴史学の方ではないが、時折挿入されるシェイクスピア作品での魚の取り上げ方も上手で、うまく解説と符合しているので楽しく読める。そして、シェイクスピア学者だけあって、視点が英国目線で、英国の魚食を知るのにとても好都合であった。
欧州の魚食の背景では以下がポイントである。
・18世紀の農業革命前は魚のほうが肉より消費されていた
・中世では1年の半分が断食日で、肉を食べることが禁じられていたことから、それらの日をフィッシュ・ディと呼んでいた
・そのフィッシュ・デイで庶民の口に入る魚として活躍したのがニシン/鯡とタラ/鱈、そしてウナギ/鰻
・物流技術等はまだまだの時代で、新鮮な魚は一部のお金持ちと海に近い者しか口に入れることはできない為、魚の保存技術が発達した
結果的に、たくさん獲れて、保存が効く魚が重宝された。

● ロンドンのうなぎ屋は日本と大違い
まずはウナギ。ウナギはとにかくたくさん捕れたらしい。そして、捕れたウナギは、保存食としてスモークするか、パイにする。パイは、具材に溶かしバターを注いで空気を遮断するので保存が効くのだ。ちなみにケンブリッジ近郊のイーリーという地がウナギの産地だったことからウナギは「イール(eel)」となったとある。

そのイギリスのウナギであるが、ロンドンでは裕福ではない方々の貴重な栄養源としてテムズ川のウナギがよく食されていたらしく、最盛期は百軒ものうなぎ屋があったと、NHKの料理紀行番組でも紹介されていた。
主な食べ方は3つ、うなぎパイ、うなぎゼリー、うなぎシチュー。お肉が安く買えるようになった昨今、さすがにうなぎパイを食べる人もいないのか、ロンドンでもパイの主流はミートパイに変わっている。

ロンドンを旅した際に、このうなぎ屋を訪ねたが、ここでもミートパイが1番売れており、大概の客はミートパイを食べていた。ミートパイにはマッシュポテト、パセリタレを添えられており、この添え物はうなぎパイも同様であった。こちらのミートパイは4£とロンドンにしては安く、味も薄味ながらなかなかであった。
ちなみに、現在は百軒もあったといううなぎ屋はもう見る影もない。そして、日本のうなぎ屋とは別で店先にいっても、あの香ばしい香りはしない。こちらのうなぎ料理の品はうなぎゼリーだから焼く工程は存在しないからである。

うなぎゼリーとは、ぶつ切りにしたウナギをレモンなどと共に煮てあり、冷やして煮こごり状のゼリーとともに食べるのだ。味は、ニシンやイワシの缶詰のような感じであり、見た目ほど不味いということはない。ただ、二度と食べることはないとは思う(笑)。特に、いただけなかったのは骨である、日本人としては「なぜ煮る前に骨くらい取らないのか?」と思う。
想像していた生臭さはさすがにないものの、川魚を食べた後の感じは残る。強い酒、ウォッカやジンとなら合うような気がした。

一方で、かつての名物だったうなぎパイは、安価な素材を美味しく食べる手段だっただけでなく、保存食としての一面をもっていたのだろうから、ちょっとこちらも食べてみたくなった。
また、別のウナギの食べ方、うなぎのスモークであるが、こちらはハンブルクやオランダやポーランドの市場の魚屋、スキポール空港でも大量に売られており、今でも普通の食材である。オランダや北ドイツ等には湿地帯が多いので、ウナギはよく捕れるのだろう。これら燻製魚は、ほどよい柔らかさで美味しく、市場で見かけると買うことにしている。


● 怪しげな体液理論とフィッシュ・デイ
ロンドン郊外のベスレム博物館の展示解説で軽く触れたが、中世の後半には怪しげな体液理論が登場する。
精神病院が牢獄や見世物小屋めいた状態だった時代が終わると、精神医療も多少なりとも医療めいた段階になる。19世紀になるとフランツ・ヨーゼフ・ガル(Franz Joseph Gall)というドイツの医師が骨相学の一種で「頭蓋鏡検査」(cranioscopy)という、耳の後ろのくぼみの形で、嘘つきや泥棒などの性癖が決まるという説を提唱した。更に、患者の写真で診断する手法、怪しげな体液理論を唱える学者もいたと言う。どれもこれも眉唾で今では見向きもされない説だか、当時は大まじめに取り組まれていたテーマだったようだ。
そして、同じ物ばかり食べていると健康のバランスが崩れるという説が体液理論の中にあったらしく、これが宗教上の断食(フィッシュ・デイ)とぶつかってしまう。民衆は「断食中でも魚だけは食べてもよい」と教会から言われていたが、体液理論では魚食だけでは健康に良くないと説かれてしまったのだ。これでは教会の教義と健康維持との間で矛楯が生じてしまう。
当時の文献には、体液理論に感化され体調不良を訴えながらもウナギや干タラを食べるしかない貧乏人のぼやきの記述がたくさんあるらしい。一方、貴族や金持ちは断食も苦にならなかったようだ。なにせ彼らの立場であれば、お金の力で魚の一種とされた甲殻類や貝はもちろん、高価ながらも新鮮な魚が手に入るからだ。

● 魚を食べないと国力が弱まる?
フィッシュ・デイには、更におもしろい話がのっていた。結婚を6回繰り返した(内2人は打ち首で離婚)ヘンリー8世の時代。彼は2回目の結婚の際のゴタゴタでイングランド国教会を発足させた。その為、イングランドはローマ(カトリック教会)と疎遠になり、フィッシュ・デイを守らなくてよくなった。すると、イングランドの国防力が弱まってしまったという話である。
からくりはこうだ。島国であるイングランドでは国防=海軍力である。フィッシュ・デイを守らなくなった英国では、魚の需要が極端に減り、漁業の衰退を招く。年の半分にもおよぶ魚食の強制がなくなった上に、貧乏な者達はウナギや干タラ、塩漬けニシン辟易していたから、魚離れが一気に進んだのだろう。そして、漁船の数は最盛期の1/3に減ってしまう。漁船は軍艦を兼ねることもあり、そもそも漁師=即戦力の海兵だったのだから、海軍力の減退は当然であり、深刻な事態であった。

そこで、エドワード6世時代(1548年)にフィッシュ・デイを強要する法律が制定される。これによって漁業の振興をはかり、台頭するスペインを見すえて海軍力を強化するためである。この本では「国民は、アルマダの海戦に勝利するために無理やり魚を食わされた」と著者はしたためている(笑)、英国民はこの当時に国から食べたくない食べ物を無理矢理強要されていたわけでもある。
そして、この海軍力補強の背景からイングランドでは、ポリティカル・フィッシュ・デイが何度も繰り返されたらしい。ただ、そもそもフィッシュ・デイは不人気な上に、宗教的な根拠もないわけだから民衆はあきれ果て、このフィッシュ・デイの徹底はどうも難しかった。
まあ、こんな具合でイングランド民は、美味しくない加工魚食ばかりを国や宗教から強いられてきたのだから、魚食が流行らず、魚料理と言えばフィッシュアンドチップスのみ、というのもわからなくもない、と英国食の現状に合点がいった。(続く)